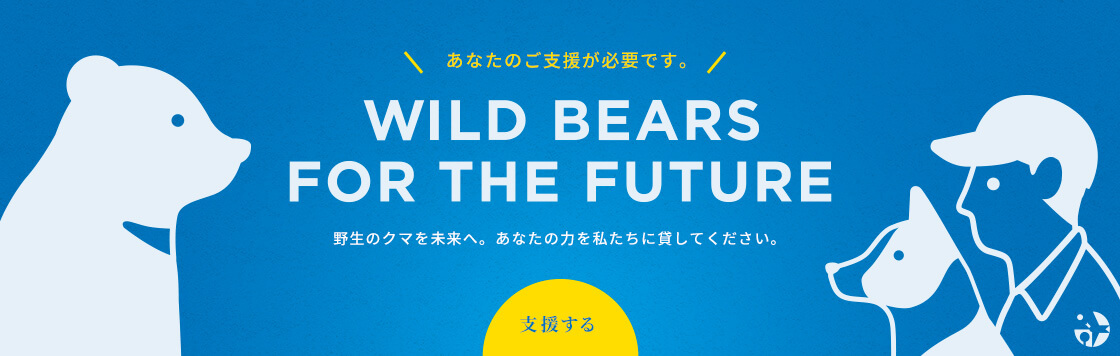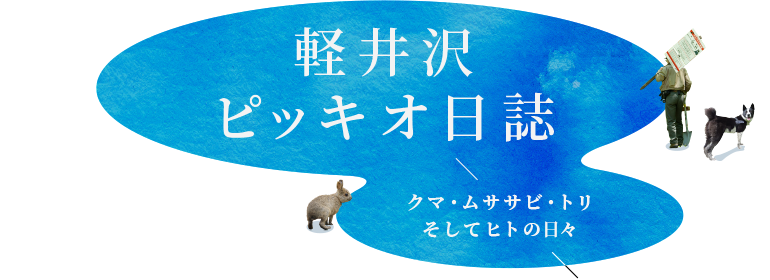

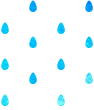
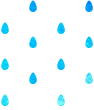
銀竜草の季節

7月3日、「軽井沢野鳥の森」の遊歩道を、鳥獣保護区管理員の業務で巡回しました。ここ数日、午後になると雷を伴う土砂降りの雨が降ったので、遊歩道にはあちこちに水の流れた跡が残されています。浅間山の軽石が堆積している地域なので、土砂流出や倒木が心配です。
さて、しっとりと湿った森で、梅雨時期ならではの植物に出会いました。木陰に真っ白な姿を現す「ギンリョウソウ」です。

ギンリョウソウ
植物は日光を浴びて二酸化炭素と水から有機物を合成し(光合成)、栄養を得ています。その際に重要な働きをするのが葉緑体に含まれるクロロフィルなどの色素ですが、純白のギンリョウソウはその色素を持っていません。つまり光合成をしないのです。
ではどのように栄養を得ているのでしょうか?以前は腐葉土から栄養を得ていると考えられていましたが、現在では菌類、つまりキノコの菌糸から栄養を得ていると考えられています。その菌類も、樹木の根と菌根を形成して、土中の肥料分や水を樹木に渡し、樹木から有機物を得て暮らしています。つまりギンリョウソウは、菌類を通して樹木から有機物を得て成長しているのです。

花には虫が集まる
ギンリョウソウは、花を咲かせ実を結ぶ時だけ地上に姿を現します。花粉や種子は、やっぱり誰かに運んで欲しいですからね。マルハナバチの仲間が訪花すると言われていますが、私は残念ながら、その瞬間をまだ見たことがありません。このとき訪れていたのは、小さなカメムシの幼虫やアリでした。
他に、7月3日の軽井沢野鳥の森で開花が確認された植物は、以下の通りです。
草の花:ムラサキツメクサ、ヒメジョオン、ダイコンソウ、ウマノミツバ、キツリフネ、サワギク、ハエドクソウ、ヤマブキショウマ、カラマツソウ、ギンリョウソウ、アカショウマ、キツネノボタン、ミツバ(順不同)
木の花:シモツケ、ヤマアジサイ、クリ(順不同)
他にケラ池周辺ではシナノキやシモツケソウ、ミソハギなどが見頃を迎えています。

ハエドクソウ
小さな花が下から順に咲き上がっていきます。実には3本の鍵があって、洋服に引っかかる「ひっつき虫」です。

ダイコンソウ
花が散るとめしべが伸び(写真上の花)、先端が鍵になってやっぱり洋服に引っかかる「ひっつき虫」になります。

ヤマアジサイ
野生のアジサイで、ここでは花が白いタイプばかりです。大きな萼を広げて花序を囲む装飾花は、虫に花の在処を知らせるためにあると言われ、実は結びません。花が終わると回転して下向きになります。何故でしょうね?
大塚
夏休みのアクティビティ/自然体験のご予約はこちらから(→ネイチャーツアー夏)。