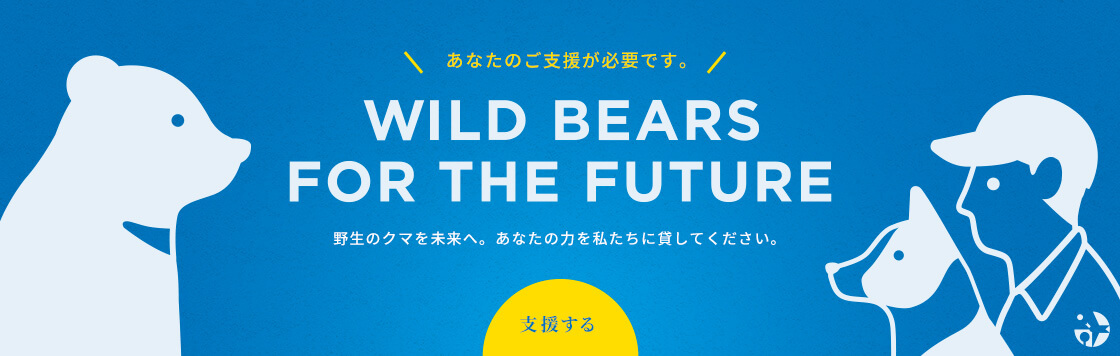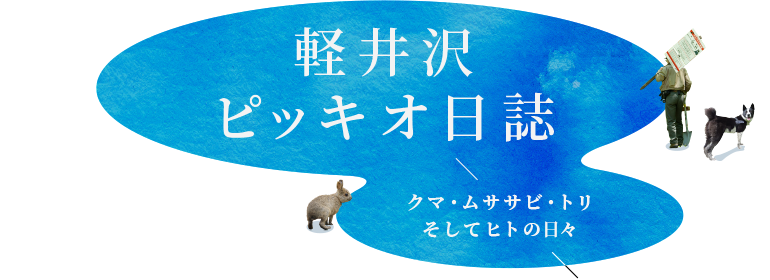

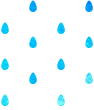
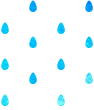
運ぶ?運ばない?

「軽井沢野鳥の森」で、ツリフネソウの花が見頃を迎えました。昨年あたりから動物に食べられた痕が増え、森の中ではずいぶんと数が減ってしまいました。おそらく増加しているニホンジカによる食害でしょう。9月3日に遊歩道を巡回したところ、小瀬林道沿いではまだたくさんのツリフネソウに出会うことができました。

ツリフネソウの花
ツリフネソウの花は、ラッパを吊り下げたような不思議な形をしています。横向きに開いた入口の手前には、2枚の花弁が斜め下向きに広がっています。そして入口の天井からは白いおしべの束が下がっていて、その中心にはめしべが隠れています。中に入ると、1枚の花弁が筒状になっていて、徐々に狭まり、最後は細くなって下向きにくるりんと巻いています。横から見ると、カメレオンの尻尾のようです。この部分を「距」と呼びます。
この花は、花粉を運んでくれる昆虫の形と大きさにぴったりサイズになっています。マルハナバチ、その中でも長い口吻を持った種類が、ツリフネソウのくるりんとした「距」の奥に溜まった蜜を吸うことができます。軽井沢での代表選手は、トラマルハナバチという種類です。

トラマルハナバチ(長い口吻と後脚の花粉だんごが見える)
トラマルハナバチは顔が長く、口にはさらに長い口吻を持っています。これで花の奥に隠された蜜を吸うことができるのです。さらには、小さな翅を畳んで、花の中に潜り込むことも躊躇しません。そして体を覆う毛は、花粉が付きやすくなっていて、体に付いた花粉は脚で器用に集め、後脚の花粉かごに集めて巣に持ち帰ります。

「どっちにしようかな?」
今の季節、ツリフネソウの群落を見ていると、大抵、トラマルハナバチがやってきます。花から花へと次々と飛び回っては、花の中に潜り込みます。

「おじゃまします」
トラマルハナバチは、手前に伸びた2枚の花弁に着地すると、モゾモゾと花の奥へと潜り込んで口吻を伸ばし、「距」の奥にある蜜を吸うと後ずさりで這い出します。この出入りするときに、頭から背中にかけて、べったりと花粉が塗りつけられます。するとおしべの先端がけずれ、めしべの頭が顔を出します。次にトラマルハナバチがやってくると、その背中に付着した花粉がめしべに付くのです。トラマルハナバチによって受粉したツリフネソウは、しばらくすると花弁を落とし、子房が膨らんで実ができます。膨らんだ実は、ぱちんと弾けて種子を飛ばし、翌春に新たなツリフネソウが芽生えます。
ところでツリフネソウのまわりを、「ブブブブ」と羽音を立てながら早いスピードで飛び回る虫がいます。

ホシホウジャク
まるでハチドリのようなその虫の正体は、蛾の仲間のホシホウジャクです。花の前でホバリングしながら、長いストローのような口吻を差し込んで蜜を吸います。

長〜い口吻
ツリフネソウの蜜は、虫に花粉を運んでもらうための報酬です。ではこのホシホウジャクは、ツリフネソウの花粉を運んでいるのでしょうか? それとも蜜をただ飲みしているだけ?

おしべに触れてない?
おしべが見える角度から撮影してみると、ホシホウジャクは長い口吻をおしべのすぐ脇に差し込んでいます。これでは花粉が付きそうにないですね。

口元にちょっと付いてる?
こちらの写真をよく見ると、口吻の付け根が、ちょっと白く見えます。ツリフネソウの花粉が付いているのかもしれません。もしかすると、ホシホウジャクもツリフネソウの花粉を運ぶことがあるのかもしれません。でもトラマルハナバチと比較すると、花粉が付着している部分の面積も、付着している花粉の量も少なそうです。ホシホウジャクがツリフネソウを受粉させられる可能性は、とても低そうですね。
大塚
ピッキオ秋のネイチャーツアー/アクティビティのご予約はこちらから→「ネイチャーツアー秋」