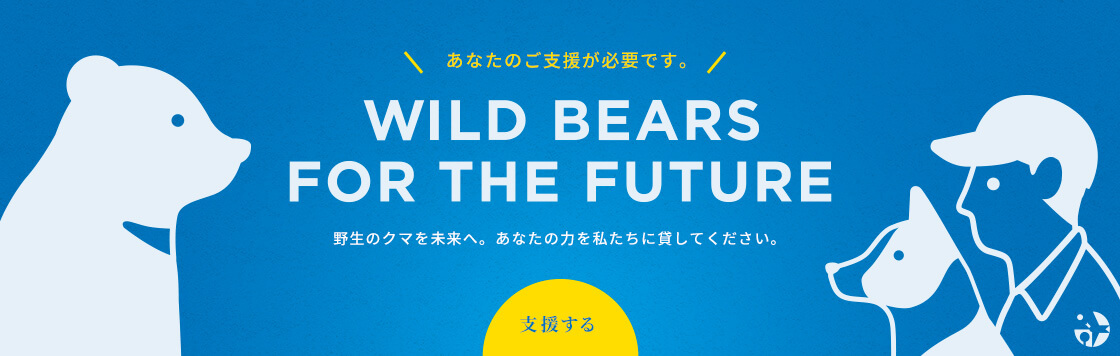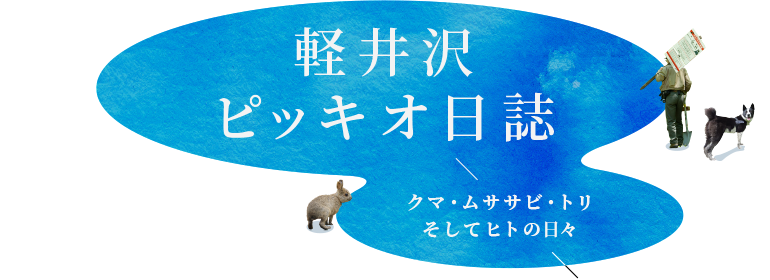

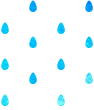
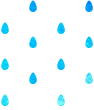
軽井沢の森に秋が訪れました

10月になりました。軽井沢はここ数日で急に涼しくなり、軽井沢野鳥の森も一気に秋らしくなってきました。遊歩道を歩くと、あちこちにクリやミズナラ、コナラのどんぐりが落ちています。今年の野鳥の森は、クリやどんぐりの実りが良いようです。

ツリバナの実
ツリバナの実も、赤く色付いて割れはじめました。赤い実は、鳥に食べられることで種子が糞と共に散布されます。ちょうど今は野鳥が南へと渡る時期。渡りの栄養補給にたくさん食べなければなりません。植物たちはそれに合わせて実が熟しているのでしょうか? 時々、南へと渡るキビタキの「ヒッ・ヒッ・ヒッ」という地鳴きが聞こえました。

どんぐり池の落葉
どんぐり池に赤い落葉が沈んでいました。ツタウルシの葉です。見上げると、ハルニレに絡んだツタウルシの紅葉が、ずいぶんと進んでいることに気付きました。

紅葉するツタウルシ
ツタウルシは、他の木の幹にへばりつきながら成長し、横枝を伸ばして葉を茂らせます。そのため、絡まれた木の梢ではなく、幹の周囲が朱に染まります。

ツタウルシの落葉
くっきりと赤と黄色に色分けされたツタウルシの落葉を見つけました。紅葉は、秋になり葉を落とす準備が始まると、日光が当たることで赤いアントシアニン色素が生成され、いっぽうで緑色のクロロフィル色素が分解されることで葉が赤くなります。葉が重なって日光が遮られていた部分は、アントシアニンが生成されないので、葉に元々含まれるカロチノイド色素で黄色くなるのです。

ミズヒキにカメムシ
ミズヒキの実は、上面が赤く下面は白い紅白になっています。これもアントシアニンの生成に日光が関わっているのでしょうね。そんなミズヒキに、緑色をしたカメムシが止まっていました。どうやらエゾアオカメムシという種類のようです。

キアゲハの幼虫
シラネセンキュウの花はまだあちこちで咲いています。その花序で、キアゲハの終齢幼虫が若い実にかじり付いていました。キアゲハの幼虫はセリ科植物を食べて育ちます。これからサナギになると、そのまま冬を越し、チョウになるのは来春でしょうね。

クロコノマチョウ
最後の写真は9月末に出会ったクロコノマチョウです。地面から枯葉が舞うようにチョウが飛び立ったので目で追うと、再び地面に静止しました。見た目も落葉にそっくりですね。成虫で越冬するチョウですが、暖かい地域に生息する種類なので、軽井沢では越冬できないかもしれません。
大塚
ピッキオ秋のネイチャーツアー/アクティビティはこちら→「ネイチャーツアー秋」